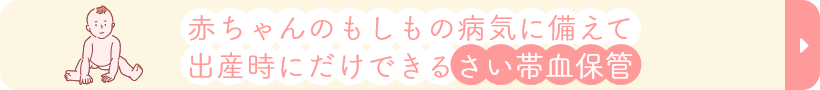突然陣痛がきたら、無事に病院までたどりつけるのか不安ですよね。
なかには近隣に産婦人科がなく、病院まで1時間以上かかる人もいるのではないでしょうか。
出産は始まってみないと分からないものですが、
「お産の進みが早かったら?」
「万が一、車の中で産むことになってしまったら?」
と考えると、とても心配になりますね。
そこで今回はいざ陣痛が来たとき、
■救急車を呼んだらダメなのか?
■救急車以外のおすすめ移動手段
■妊婦さんが救急車を呼ぶべき3つのケース
について解説していきます。
もうすぐ出産で「いざ陣痛が始まったときにどう動いたらよいのか不安…」という人は、ぜひ参考にしてください。
陣痛で救急車を呼んだらダメなのか?

陣痛や破水だけでは、すぐに救急車を呼ぶ必要はありません。
個人差はありますが陣痛・破水の場合、すぐには赤ちゃんが生まれません。
産婦人科の説明でも、
陣痛がきたら産婦人科に電話をして、家族の運転で来院する・もしくはタクシーを呼ぶ と言われるケースが多いでしょう。
妊婦さんが絶対救急車を呼んではいけない、という決まりはありませんが、救急車は緊急性の高い人のための移動手段だと考えましょう。
陣痛がきた!救急車以外でおすすめの交通手段は陣痛タクシー
タクシーはいつでも手配できて、自家用車がない場合や、家族が仕事などですぐに対応できない場合も安心です。
とくに「陣痛タクシー」は、出産を控えた人を病院へ送ることを目的としていて、妊婦さんの強い味方です。
ただし陣痛タクシーを利用するためには、事前にタクシー会社へ「事前登録届出書」を提出する必要があります。
以下は、事前登録届出書の必要記載事項例です。
■名前
■出産予定の医療機関
■連絡先
■出産予定日
■タクシーが迎えに行く場所
陣痛タクシーを利用するためには、遅くとも臨月までには事前登録をしておきましょう。
ただしすべてのタクシー会社が、陣痛タクシーに対応しているわけではありません。
自分の住所近くで、陣痛タクシーを手配している会社を探す必要があります。
また陣痛が来たら、すぐに陣痛タクシーを呼ぶのではなく、まずはかかりつけの産婦人科に電話してから、陣痛タクシーを呼ぶようにしましょう。
タクシーが到着するまでに
■家族へ連絡、入院するのための荷物を用意
をしておくことしておくことも大切です。
陣痛のときはNG!避けるべき3つの移動手段

陣痛がきた際に、以下の3つのような移動手段は避けるべきです。
■自分で車を運転する
■電車やバスなど交通機関
■徒歩
順番に内容を解説していきます。
NGの手段1:自分で車を運転する
絶対に避けるべき移動手段は、自分で車を運転して移動することです。
痛みが強くなって運転ができなくなる可能性があり、何より危険です。
万が一事故を起こしてしまったら、あなたやおなかの赤ちゃんに生命の危険が及びます。
また周りの人を巻き込んでしまうことにもなるでしょう。
くれぐれも陣痛中の運転はしないようにしましょう。
NGの手段2:バスや電車などの公共交通機関
電車やバスなどの公共交通機関は、妊婦さんの体調によって柔軟な対応ができないため、避けるのが無難です。
公共交通機関は、個人の都合で停めることは難しく、強い陣痛や破水が起きた場合、適切な処置ができない可能性があります。
また、事故や渋滞による遅延や長時間の停車が起こる可能性もあります。
NGの移動手段3:徒歩
歩くと陣痛を促進する効果があるため、避けたほうがよいとは言い切れません。
しかし移動の途中で破水や陣痛が強く、動けなくなる場合もあるため、病院が遠い場合、徒歩は避けたほうが安全です。
妊婦さんがすぐに救急車を呼ぶべき3つのケース

基本的に陣痛・破水で救急車を呼ぶ必要はありません。
しかし以下の症状がある場合は、ただちに救急車を呼ぶべきです。
■下腹部に激痛を感じる・大量出血している
■動けないほどの頭痛がある
■その他緊急性がある
順番に内容をくわしく解説していきます。
ケース1:下腹部に激痛を感じる・大量出血している
下腹部に激痛や大量出血がある場合「常位胎盤早期剥離」の可能性があるため、すぐに救急車を呼びましょう。
胎盤は通常、お産が終わると自然に体外に出てくるものです。
しかし常位胎盤早期剥離はお産前に胎盤が剥がれてしまい、激痛や大量出血を伴ううえ、あなたや赤ちゃんが危険な状態に陥ってしまいます。
常位胎盤早期剝離は「妊娠高血圧症候群」などの妊婦さんが罹りやすいと言われています。
ケース2:動けないほどの頭痛がある
妊娠後期になると、妊娠高血圧症候群のリスクも高まります。
妊婦さんの血圧が異常に高くなってしまう症状で、母子ともに危険が高くなります。
異常な頭痛に襲われた場合は、血圧が急激に上がっている可能性もあり、救急車を呼ぶ必要があります。
これは私の知人の話ですが、予定日も近づき、いよいよ出産という日の朝。
今まで経験したことのない頭痛に襲われ目を覚まし、何かおかしいと思い、慌てて産婦人科に電話したそうです。
家族に付き添ってもらい、やっとのことでかかりつけの産婦人科に到着。
先生に診てもらったところ、血圧がかなり高くなっており、母体・胎児ともに危険な状態だったということがわかりました。
助産師さんが救急車を呼び、先生も一緒に救急車に乗ってNICUのある大きな病院に搬送されました。
幸い血圧は下がり、予定日間近ということもありタイミングよく陣痛もきたそうで、無事お産をすることができたそうです。
いままで妊婦健診で血圧が高い数値だったということもなかったため、とても驚いたと話していました。
ケース3:緊急性がある
以下のような緊急を要する場合は、救急車を呼ぶべきでしょう。
■台風や大雪で、タクシーや自家用車が使えない
■陣痛の進み方が非常に早い(特に経産婦さん)
■陣痛がどんどん強まっているのに、渋滞で車が動かない
救急車を呼ぶべきなのか、自身で判断がつかないこともあるでしょう。
救急車を呼ぶべきか迷ったときは、まずはかかりつけの産婦人科や、24時間体制の救急電話相談ダイヤル(#7119)に連絡をして状況を説明し、指示を仰ぎましょう。
陣痛で救急車を呼んだときの料金はどのくらい?

救急車の利用料は基本的には無料ですが、
・緊急性が低いと判断された場合
・搬送先が200床以上(※1)の病院の場合
は救急車の料金とは別に「特定療養費(※1)」と呼ばれる療養費が7,000円以上(※2)発生する場合があります。
出典
自治体によっては救急車を呼ぶ妊婦さんへの支援も
 自治体によっては、妊婦さんに母子手帳を交付する際、消防署に妊婦さんの住所や出産予定施設などを登録する仕組みをとっている場合もあります。
自治体によっては、妊婦さんに母子手帳を交付する際、消防署に妊婦さんの住所や出産予定施設などを登録する仕組みをとっている場合もあります。
万が一救急車を手配する必要があった場合も、あらかじめ消防署に妊婦である情報が登録されているため、適切な対応をとってもらえる可能性が高まります。
まとめ
大切なのは陣痛に備えて、どのように病院へ向かうか考えておくことです。
陣痛の際に、かならずしもパートナーや家族がいるとは限りません。
陣痛や破水がいつ起こっても対応できるよう、前もって移動手段を考えておきましょう。
産婦人科が遠方にしかないという人は、かかりつけの産婦人科で、陣痛が起こったらどのように病院まで来たらよいのかも相談してみてください。
陣痛がきたときの対応や注意すべき点など、相談にのってもらえるでしょう。
また陣痛や破水が起きるすると、冷静でいられないこともあります。
陣痛がきたら、破水してしまったらどうするのかを家族と一緒に確認しておくと心強いですね。
チャンスは出産時の一度きり。赤ちゃんの将来の安心に備えるさい帯血保管とは
うまれてくる赤ちゃんのために、おなかに赤ちゃんがいる今しか準備できないことがあるのをご存知ですか?
それが「さい帯血保管」です。
さい帯血とは、赤ちゃんとお母さんを繋いでいるへその緒を流れている血液のことです。
この血液には、「幹細胞」と呼ばれる貴重な細胞が多く含まれており、再生医療の分野で注目されています。
このさい帯血は、長期にわたって保管することができ、現在は治療法が確立していない病気の治療に役立つ可能性を秘めています。
保管したさい帯血が、赤ちゃんやご家族の未来を変えるかもしれません。
しかし採取できるのは、出産直後のわずか数分間に限られています。
採血と聞くと痛みを伴うイメージがあるかと思いますが、さい帯血の採取は赤ちゃんにもお母さんにも痛みはなく安全に行うことができます。
民間さい帯血バンクなら、赤ちゃん・家族のために保管できる
さい帯血バンクには、「公的バンク」と「民間バンク」の2種類があり、公的バンクでは、さい帯血を第三者の白血病などの治療のために寄付することができます。
一方民間バンクでは、赤ちゃん自身やそのご家族の将来のために保管できます。
現在治療法が確立されていない病気に備える保険として利用できるのが、この民間さい帯血バンクです。
ステムセル研究所は、国内シェア約99%を誇る国内最大の民間さい帯血バンクです。
ステムセル研究所が選ばれる理由

・1999年の設立以来20年以上の保管・運営実績あり
・民間バンクのパイオニアで累計保管者数は7万名以上
・全国各地の産科施設とのネットワークがある
・高水準の災害対策がされた国内最大級の細胞保管施設を保有
・厚生労働省(関東信越厚生局)より特定細胞加工物製造許可を取得
・2021年6月東京証券取引所に株式を上場
詳しい資料やご契約書類のお取り寄せは資料請求フォームをご利用ください。
さい帯血を保管した人の声
■出産の時だけのチャンスだから(愛知県 美祐ちゃん)
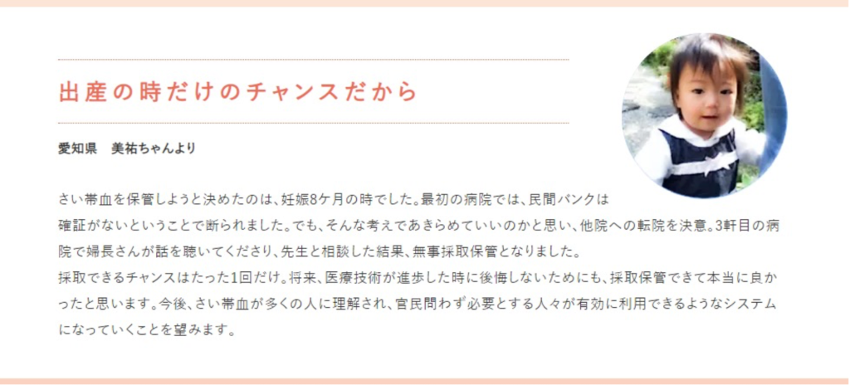
■さい帯血が本当の希望になりました(東京都 M・Y様)
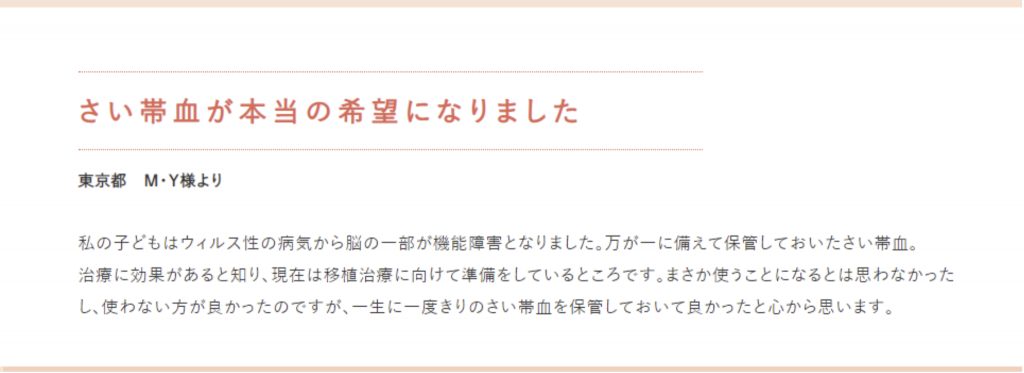
※ほかの保管者のから声はこちら
さい帯血保管は、赤ちゃんへの「愛」のプレゼント。
心も体も出産に向けた準備をしながら、赤ちゃんに会えるまでのもう少しの期間、ぜひ幸せな気持ちで過ごしてくださいね。
▼さい帯血保管について、もっと詳しく
この記事の監修者

坂田陽子
経歴
葛飾赤十字産院、愛育病院、聖母病院でNICU(新生児集中治療室)や産婦人科に勤務し、延べ3000人以上の母児のケアを行う。
その後、都内の産婦人科病院や広尾にある愛育クリニックインターナショナルユニットで師長を経験。クリニックから委託され、大使館をはじめ、たくさんのご自宅に伺い授乳相談・育児相談を行う。
日本赤十字武蔵野短期大学(現 日本赤十字看護大学)
母子保健研修センター助産師学校 卒業
資格
助産師/看護師/国際認定ラクテーションコンサルタント/ピーターウォーカー認定ベビーマッサージ講師/オーソモレキュラー(分子整合栄養学)栄養カウンセラー