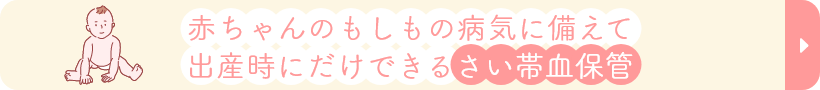「妊婦健診前なのに体重が増えすぎてしまった」「妊婦でも安心して体重を管理するコツを知りたい」
と悩んでいる人も多いのではないでしょうか。
逆に
「つわりがひどくて、妊婦なのに体重が増えない」
と悩んでいる人もいるでしょう。
妊娠中の体重管理は、母子ともに健康であるために大切。
とはいえ、体重管理は本当に難しいですよね。
そこで、
■妊婦さんの理想の体重目安
■妊婦さんが、上手に体重管理をするコツ
■体重の増えない妊婦さんができること
などをご紹介します。
体重管理で悩んでいる妊婦さんは、ぜひ参考にしてくださいね。
きっと適正体重を守れるようになりますよ。
妊婦さんの体重管理幅はBMIによる

厚生労働省では、妊娠前の自身のBMIによって体格を4つに分け、望ましい体重増加量を下記のように提示しています。
| BMI値 | 望ましい体重増加量 |
| BMI18.5未満(低体重) | 推奨する増加量12~15kg
|
| BMI18.5以上25.0未満(普通) | 推奨する増加量10~13kg
|
| BMI25.0以上30.0未満(肥満1度) | 推奨する増加量7~10kg
|
| BMI30.0以上(肥満2度以上) | 5kgまでを上限に個別対応
|
ちなみにBMIは、下記の計算で求められます。
BMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)
例:妊娠前の体重が54kg、身長が160㎝だった場合…
54(kg)÷1.6(m)÷1.6(m)=21.09
低体重、普通の区分にある妊婦さんは、1週間で0.3~0.5kgの増加量を目安にするとよいでしょう(注1)。
母体や赤ちゃんへの負担を考えても、緩やかに増加させていくことがポイントです。
出典
(※1)「妊娠期の至適体重増加チャート」について|厚生労働省
妊婦さんの体重が増えやすい理由

胎児を守るための皮下脂肪、出産時の出血を補うための血液量の増加など、ホルモンの働きが影響しています。
妊婦さんの体は胎盤や羊水、胎児の重さで増えるのはもちろんですが、それ以外の要因でも太りやすくなっているのです。
妊婦さんの体重が増えすぎると、どんな影響がある?
「太りやすく」はなっているものの「太りすぎ」てしまうと、出産時や胎児にも悪影響が起こりやすくなります。
たとえば「妊娠糖尿病」「妊娠高血圧症候群」のほか、産道に脂肪が付きすぎて、出産時に胎児が下りてきにくくなるなど、さまざまなトラブルの原因にもなるのです。
妊婦さんに効果的な3つの体重管理のコツ

そこで、妊婦さんに効果的な体重管理のコツを3つご紹介します。具体的には、①ご自分の体重を把握すること、②軽めの運動を取り入れること、③食生活を見直すということです。ご自身のご体調に合わせて、取り入れられる点があれば是非お試しください。より詳しくご説明します。
体重管理法1:自身の体重を把握する
今現在どれだけの体重があるのか、自分の体重を把握しましょう。きちんと数字を見るだけでも、どのぐらいの変化があるのか視覚的に把握できるので効果的です。妊婦健診での体重管理は数週間単位になりますので、きちんと把握する場合は、毎朝図るとよいでしょう。
体重管理法2:軽めの運動をする
妊娠初期は慎重に過ごす必要がありますが、妊娠中期に入った妊娠16週頃から、主治医に相談したうえで、軽めの運動をしてみるとよいでしょう。
マタニティヨガは出産時の呼吸練習や、骨盤を整える効果も得られます。
妊婦さん同士で会話をするチャンスもあり、友だち作りにも最適でしょう。
近所を散歩してみるだけでも気持ちがよいものです。
途中で体調が悪くなった時のためにも、家族と一緒だと安心かもしれません。
体重管理法3:生活を見直す
妊娠中に必要となる摂取エネルギー量は妊娠前よりも増えますが、炭水化物や糖分は増やさず
・魚
・肉
・野菜
を増やしましょう。
基本的には、1日3食バランス良い食事が理想です。主食、主菜、副菜が揃っていて、さらに乳製品や果物があると良いです。
主菜には、肉や魚を選び、鉄やカルシウムなどの栄養素を取り入れるようにしましょう。鉄分は、血液を作る為に大切な栄養素ですし、カルシウムは赤ちゃんの骨や歯を作る大切な栄養素です。また、副菜には野菜を積極的に取るのがおすすめです。中でも、緑黄色野菜に含まれる葉酸は、お腹の赤ちゃんの成長や神経管閉鎖障害の発症リスク低減のために必要な栄養素です。
【危険】妊婦さんが体重管理をしないリスク

体重管理は増えないようにセーブするばかりではありません。
主治医に「体重を増やしたほうが良いでしょう」と言われている妊婦さんもいます。
厚生労働省によると、妊娠前の体格区分が「低体重」だった女性の、妊娠中の体重増加が7kg未満だった場合は、低出生体重児を出産するリスクが高いといわれています(注2)。
リスクを避けるためにも、妊娠前の体格区分が「低体重」だった場合の推奨増加量「12~15kg」増を目指したいところです。
出典
(※2)「妊娠期の至適体重増加チャート」について|厚生労働省
まとめ
妊婦さんの体重管理は、常に頭に置いておく必要があり、悩ましいお気持ちになる方が多いかと思います。今回ご紹介しました「体重管理のコツ」を是非ご参考にしてみてください。何に手をつけてよいか迷う場合は、まずご自分の体重を把握してみてことから始めてみませんか?増えすぎている場合は、適切な数値に戻るように運動や食生活を見直すきっかけになるはずです。また、体重を増やした方が良い場合は、食生活を中心に見直すなど解決方法をお考えいただければと思います。体重管理ができれば、ママや赤ちゃんへのリスクを減らす事にもつながりますので、是非前向きにお考え下さい。
チャンスは出産時の一度きり。赤ちゃんの将来の安心に備えるさい帯血保管とは

うまれてくる赤ちゃんのために、おなかに赤ちゃんがいる今しか準備できないことがあるのをご存知ですか?
それが「さい帯血保管」です。
さい帯血とは、赤ちゃんとお母さんを繋いでいるへその緒を流れている血液のことです。この血液には、「幹細胞」と呼ばれる貴重な細胞が多く含まれており、再生医療の分野で注目されています。
このさい帯血は、長期にわたって保管することができ、現在は治療法が確立していない病気の治療に役立つ可能性を秘めています。保管したさい帯血が、赤ちゃんやご家族の未来を変えるかもしれません。
しかし採取できるのは、出産直後のわずか数分間に限られています。採血と聞くと痛みを伴うイメージがあるかと思いますが、さい帯血の採取は赤ちゃんにもお母さんにも痛みはなく安全に行うことができます。
民間さい帯血バンクなら、赤ちゃん・家族のために保管できる
さい帯血バンクには、「公的バンク」と「民間バンク」の2種類があり、公的バンクでは、さい帯血を第三者の白血病などの治療のために寄付することができます。
一方民間バンクでは、赤ちゃん自身やそのご家族の将来のために保管できます。現在治療法が確立されていない病気に備える保険として利用できるのが、この民間さい帯血バンクです。
ステムセル研究所は、国内シェア約99%を誇る国内最大の民間さい帯血バンクです。
ステムセル研究所が選ばれる理由

・1999年の設立以来20年以上の保管・運営実績あり
・民間バンクのパイオニアで累計保管者数は7万名以上
・全国各地の産科施設とのネットワークがある
・高水準の災害対策がされた国内最大級の細胞保管施設を保有
・厚生労働省(関東信越厚生局)より特定細胞加工物製造許可を取得
・2021年6月東京証券取引所に株式を上場
詳しい資料やご契約書類のお取り寄せは資料請求フォームをご利用ください。
さい帯血を保管した人の声
■出産の時だけのチャンスだから(愛知県 美祐ちゃん)
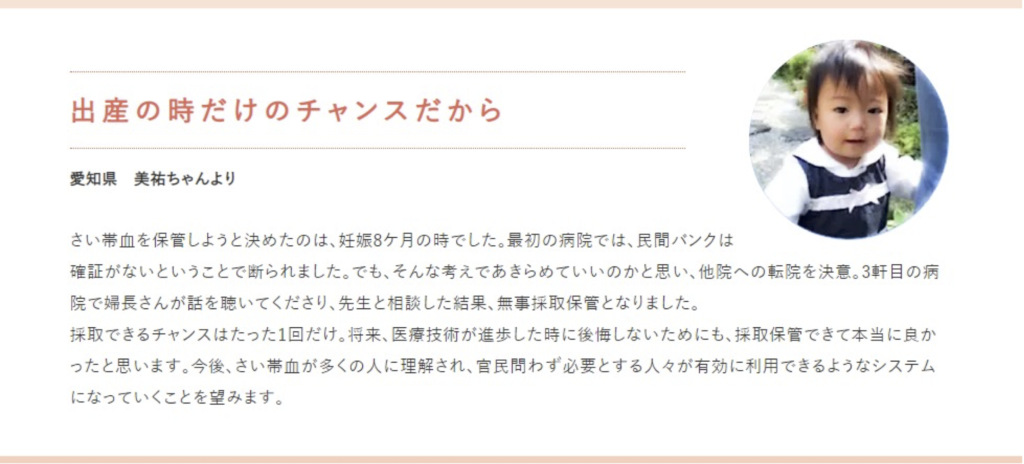
■さい帯血が本当の希望になりました(東京都 M・Y様)
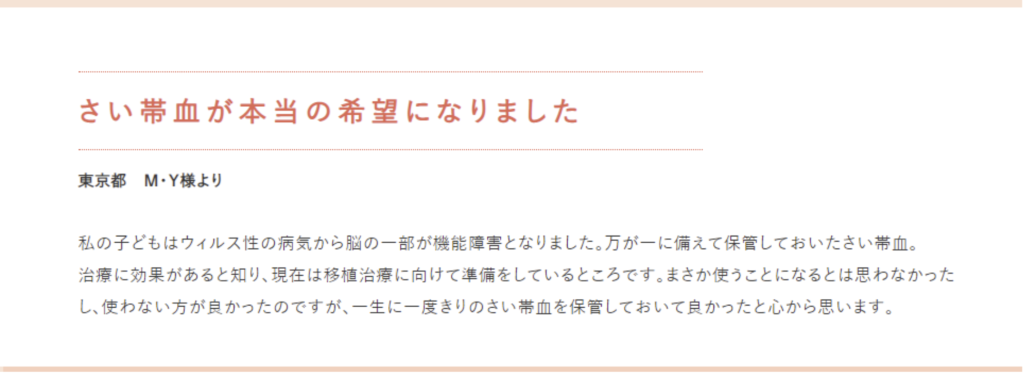
※ほかの保管者のから声はこちら
さい帯血保管は、赤ちゃんへの「愛」のプレゼント。
赤ちゃんに会えるまでのもう少しの期間、ぜひ少しでも快適に、幸せな気持ちで過ごしてくださいね。
この記事の監修者

坂田陽子
経歴
葛飾赤十字産院、愛育病院、聖母病院でNICU(新生児集中治療室)や産婦人科に勤務し、延べ3000人以上の母児のケアを行う。
その後、都内の産婦人科病院や広尾にある愛育クリニックインターナショナルユニットで師長を経験。クリニックから委託され、大使館をはじめ、たくさんのご自宅に伺い授乳相談・育児相談を行う。
日本赤十字武蔵野短期大学(現 日本赤十字看護大学)
母子保健研修センター助産師学校 卒業
資格
助産師/看護師/国際認定ラクテーションコンサルタント/ピーターウォーカー認定ベビーマッサージ講師/オーソモレキュラー(分子整合栄養学)栄養カウンセラー