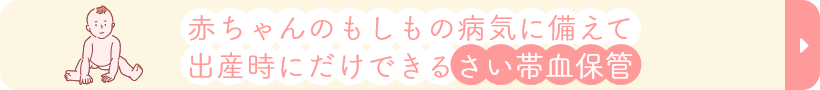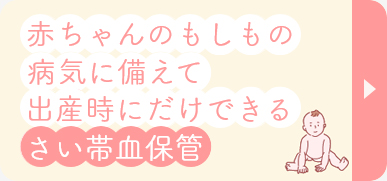妊娠中から、新生児のお世話で心配なことはたくさんありますよね。
そのひとつが、夜泣きではないでしょうか。
新生児は睡眠リズムが整っていないため、夜中に起きて泣き出してしまうケースがあります。
夜泣きが続くと自身も疲れてしまい、近所の目も気になるでしょう。
正しい対策を行えば、夜泣きは減らせる可能性があります。
この記事では、おもに以下の内容を解説していきます。
- ・新生児が夜泣きする原因
- ・夜泣きはいつまで続くのか
- ・夜泣きの対策3つ
この記事を読むと、出産後に安心して夜泣きの対応ができるようになりますよ。
新生児が夜泣きする3つの原因

夜泣きの原因は、主に次の三つと言われています。感情を訴えている場合、睡眠リズムが整っていない場合、体調不良を起こしている場合です。ただし、夜泣きの原因は明確化されておらず、生理的な現象という説もあります。
原因1:感情を訴えている
感情とは、快や不快を表すことと言えますが、新生児の場合には、おむつが汚れた、おなかがすいた、光がまぶしい、暑すぎるなどの不快感を泣くことで訴えています。また、甘えたいという感情も泣くことで訴える場合もあるかと思います。
原因2:睡眠リズムが整っていない
新生児は睡眠リズムが整っておらず、日中の睡眠時間と夜間の睡眠時間はほぼ同じと言われています。睡眠時間は16~20時間/日で、1~4時の睡眠ごとに1~2時間の起床を繰り返します(※1)。新生児の睡眠サイクルは、大人の睡眠サイクルとは大きく異なります。このような、睡眠リズムや睡眠サイクルが影響して、夜泣きの原因となることがあります。
出典
(※1)未就学児の睡眠指針|厚生労働省(2018年3月発行)
原因3:体調不良を起こしている
新生児は免疫力が弱く、病気にかかりやすい状態です。何らかの体の不調や異常があった場合には、まだお話して伝えることはできないため、これらを泣いて表現するケースもあり、夜泣となる場合があります。
新生児の夜泣きはいつまで続く?

- ・個人差がある
新生児の夜泣きについては、個人差も多いと言われていますが、株式会社エムティーアイが運営するルナルナによると、約54%の新生児が生後12ヶ月までに夜泣きがおさまる結果を公表(※2)しています。
出典
(※2)【ルナルナ みんなの声】「夜泣き」についての調査|ルナルナ
新生児が泣き止まない!夜泣きの対策3点

新生児が夜泣きするときの対策方法を3つご紹介します。それは、「生活リズムをつくる」、「お腹にいたときのような環境をつくる」、「ドライブや散歩をする」ということです。ただし、先に赤ちゃんのおむつが汚れていないかの確認や、部屋が暑すぎたり寒すぎたりしていないかを確認したうえで、試してみてください。
対策1:生活リズムをつくる
生活リズムを整えるには、先ず朝起きたらカーテンを開けて光を浴び、夜になったら部屋を暗くして眠る準備をすることがポイントです。そして、日中にはよく遊ばせるなどして、日光(紫外線)を浴びたり体を動かしたりすることで「セロトニン」の分泌が活性化されると、夜に「メラトニン」の分泌も増え、寝つきがよくなると言われています。朝7時に起きて、昼はよく遊ばせると、夜にぐっすり眠れる習慣が身につく(※3)とも言われています。また、夜眠りにくくなるため、日中に昼寝をさせ過ぎないのもポイントです。
(※3)【第57号】赤ちゃんの夜泣きその2~夜泣き改善編 NPO法人赤ちゃんの眠り研究所 中西美好|大阪市役所(2022年10月30日掲載)
対策2:お腹にいたときのような環境をつくる
赤ちゃんに安心感を与えてあげるため、抱っこしながら、体を軽くゆらゆら揺らす、背中をさする、声をかけるなどするとよいでしょう。おくるみやバスタオルに包んで、手足が動かないようにして抱っこすると、お腹の中にいた時のような環境になります。また、妊娠中に聴いていた音楽があるならば、和んだり安らぐ効果があるかもしれませんので、是非親子で聴いてみてください。
対策3:ドライブや散歩をする
不思議ですが、抱っこして外に出てお散歩したり、車でドライブすると夜泣きがピタっと泣き止むことがあります。お散歩で新鮮な空気に触れて、赤ちゃんもリフレッシュするのかもしれませんし、ドライブですと車の揺れやが眠気を誘ってくれるのでしょうか。新生児だけでなく、大人の気分転換にもなったりしますよ。
受診サインがなければ、肩の力を抜いてみる

理由があっても無くても泣くのが赤ちゃん。わかっていても、ママやパパは赤ちゃんが泣くたびにハラハラしながら対処し、心配もしますよね。さらには、ママやパパが起きている昼間に赤ちゃんが泣くのと、ママやパパが疲れて眠い夜に赤ちゃんが泣くのでは、負担も違ってくるでしょう。
特に、赤ちゃんの脳が発達して夜泣きが始まる時期にはママの体も回復期に入っていますが、赤ちゃんが新生児期だとママもまだ産褥期。そんな中での夜泣きは、心身ともに負担が大きいかもしれません。
オムツも替えた、ミルクもあげた、汗もかいていない、一体どうして?と万策尽きて途方に暮れることもあるかと思います。そんなときは、万が一のために新生児の受診サインをチェックしてみましょう。
- ・38℃以上の熱がある
- ・ぐったりしている
- ・下痢やおう吐がある
- ・顔色が青白い/突然青白くなる
上記の症状があった場合は、かかりつけ医や小児救急電話相談《#8000》へ相談することをおすすめします。
受診のサインに当てはまらなかった場合、何をしても泣き止まないということは、泣くだけの元気はあるということですから、近くで赤ちゃんの様子を見守りながら、肩の力を抜いてみてくださいね。
【体験談】新生児の夜泣きとどう向き合った?
- ・筆者の娘は2人とも新生児期~1歳前まで夜泣きが酷かった
- ・ひどい時は、1時間半おきに目覚めて泣く日が1か月以上続くことも→夜中、泣きやまない娘と一緒に、眠れない辛さもあいまって自分も大泣きしたこともしょっちゅう
- ・1人目のときはミルクだったので、次の授乳時間までひたすら抱っこ→ミルク作りは夫に代わってもらうなどして乗り切った。そばで添い寝をするようになってから、手でトントンするだけで寝るように→成長とともに夜泣きの頻度も少しましになった
- ・2人目は母乳だったので、泣くたびにとにかく母乳を吸わせていた→実家の近くに住んでいたので、昼間に娘2人を連れて実家を訪れ、昼寝させてもらって乗り切った→こちらも成長とともに夜泣きは少しずつましになっていった
- ・我が家の娘たちの場合は、1歳過ぎ頃、ミルク・母乳とも授乳期が終わると同時ぐらいに夜泣きがなくなった
- ・2人とも明確に夜泣きの原因はわからなかった。→周りのママ友の話を聞いていても「寝る子は何しても寝る」「寝ない子は何しても寝ない」「夜泣きが始まる時期も終わる時期も、子どもそれぞれ」→睡眠リズムは赤ちゃん各々の個性だと、ある程度割り切りも必要だと感じた
- ・ただし夜泣きに付き合うときの「眠りたいのに眠れない」状態が、それも長期間続くと、心身共に非常にダメージが大きい
→夜泣き中は、夫・実家・自治体のサポート制度などをフル活用して、昼でも夜でも、とにかく自分の睡眠時間を少しでも確保して。夜泣きは一生続かない。家事も適当でも死なない。自分と赤ちゃんが生きていればOKぐらいの気持ちで、夜泣き期間をなんとか乗り切って。いつか嘘みたいに、一晩まとめて寝てくれる日が、あるとき突然訪れます。そんな日が1日も早くきますように。
まとめ
睡眠リズムが整うまでは昼夜問わず泣きますが、正常に発達している証拠です。
赤ちゃんが泣いたら、まずは抱っこ。そして不快なことを取り除いてあげましょう。
泣き止まなかった場合でも、受診が必要な症状は無いかを確認したら、ママも一息つきましょう。
もちろん家族の協力は必要不可欠。
抱っこを交代で行うなど、パパや周りの家族と一緒に子育てをスタートさせるきっかけになると良いですね。
一人で頑張りすぎず、抱え込まず。ママのリラックスを赤ちゃんにも伝えるつもりで、夜泣きを乗り切りましょう。
チャンスは出産時の一度きり。赤ちゃんの将来の安心に備えるさい帯血保管とは

うまれてくる赤ちゃんのために、おなかに赤ちゃんがいる今しか準備できないことがあるのをご存知ですか?
それが「さい帯血保管」です。さい帯血とは、赤ちゃんとお母さんを繋いでいるへその緒を流れている血液のことです。この血液には、「幹細胞」と呼ばれる貴重な細胞が多く含まれており、再生医療の分野で注目されています。
このさい帯血は、長期にわたって保管することができ、現在は治療法が確立していない病気の治療に役立つ可能性を秘めています。保管したさい帯血が、赤ちゃんやご家族の未来を変えるかもしれません。
しかし採取できるのは、出産直後のわずか数分間に限られています。採血と聞くと痛みを伴うイメージがあるかと思いますが、さい帯血の採取は赤ちゃんにもお母さんにも痛みはなく安全に行うことができます。
民間さい帯血バンクなら、赤ちゃん・家族のために保管できる
さい帯血バンクには、「公的バンク」と「民間バンク」の2種類があり、公的バンクでは、さい帯血を第三者の白血病などの治療のために寄付することができます。
一方民間バンクでは、赤ちゃん自身やそのご家族の将来のために保管できます。現在治療法が確立されていない病気に備える保険として利用できるのが、この民間さい帯血バンクです。
ステムセル研究所は、国内シェア約99%を誇る国内最大の民間さい帯血バンクです。
ステムセル研究所が選ばれる理由

- ・1999年の設立以来20年以上の保管・運営実績あり
- ・民間バンクのパイオニアで累計保管者数は7万名以上
- ・全国各地の産科施設とのネットワークがある
- ・高水準の災害対策がされた国内最大級の細胞保管施設を保有
- ・厚生労働省(関東信越厚生局)より特定細胞加工物製造許可を取得
- ・2021年6月東京証券取引所に株式を上場
詳しい資料やご契約書類のお取り寄せは資料請求フォームをご利用ください。
さい帯血を保管した人の声
■出産の時だけのチャンスだから(愛知県 美祐ちゃん)
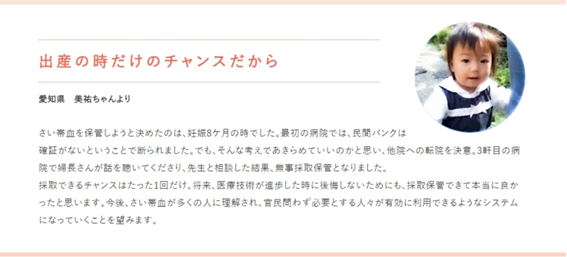
■さい帯血が本当の希望になりました(東京都 M・Y様)
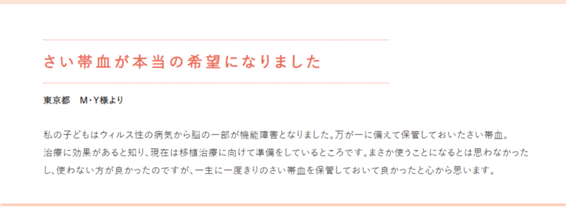
※ほかの保管者のから声はこちら
さい帯血保管は、赤ちゃんへの「愛」のプレゼント。
赤ちゃんに会えるまでのもう少しの期間、ぜひ少しでも快適に、幸せな気持ちで過ごしてくださいね。
▼さい帯血保管について、もっと詳しく
この記事の監修者

坂田陽子
経歴
葛飾赤十字産院、愛育病院、聖母病院でNICU(新生児集中治療室)や産婦人科に勤務し、延べ3000人以上の母児のケアを行う。
その後、都内の産婦人科病院や広尾にある愛育クリニックインターナショナルユニットで師長を経験。クリニックから委託され、大使館をはじめ、たくさんのご自宅に伺い授乳相談・育児相談を行う。
日本赤十字武蔵野短期大学(現 日本赤十字看護大学)
母子保健研修センター助産師学校 卒業
資格
助産師/看護師/国際認定ラクテーションコンサルタント/ピーターウォーカー認定ベビーマッサージ講師/オーソモレキュラー(分子整合栄養学)栄養カウンセラー