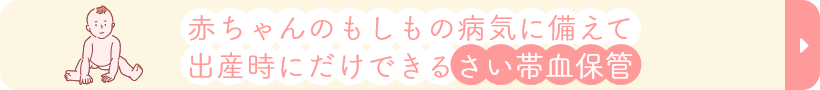初めての出産をひかえていると、「出産(分娩)はどんな流れで進んでいくのだろう?」と不安や心配になりますよね。
実は分娩の過程は3つに分かれ、陣痛の間隔や感じる痛みも異なります。
また初産であれば、陣痛が始まってから胎児が分娩されるまで12~16時間ほどかかるのです。
この記事では、おもに以下の内容を解説していきます。
・分娩が始まる3つのサイン
・自然分娩の流れ
・分娩後の生活
この記事を読むと分娩の流れがわかるため、出産前に心の準備ができますよ。
分娩開始までの流れと3つのサイン

自然分娩の開始前には、以下3つのサインがあります。
・おしるし
・陣痛
・破水
3つのサインが現れる順番には、個人差があります。
いずれかのサインが見られたら、分娩が近いと考えておきましょう。
分娩開始のサイン1:おしるし
子宮口が開き始めると出てくる、出血が混じったおりもののことです。
出産が近づいてきたサインではありますが、おしるしだけで分娩になることはありません。
清潔なナプキンをあて、ほかのサインが出てくるまで、慌てず落ち着いて普段通りの生活を続けましょう。
分娩開始のサイン2:陣痛
最初は不規則に、次第に規則的でおなかの痛みが強い張りに変わっていきます。
一般的に初めての出産では、陣痛が始まってからお産が終わるまで12~16時間前後かかります。
ただ個人差が大きく、20時間以上かけてお産をする人も。
10分間隔の痛み(もしくは1時間に6回以上の痛み)が定期的に訪れるようになったら、陣痛が始まりといわれています。
ただし上記の段階では、分娩まではまだ長い時間を要します。
かかりつけの医療機関からは、連絡するタイミングなどの説明(たとえば、初産婦なら「10分以内の規則的に繰り返す陣痛を感じたら連絡してください」など)があるでしょう。
そのため痛みを感じ始めたら、まずは陣痛の間隔をカウントするようにしましょう。
出典:
産科における看護師の業務|日本産婦人科医会(2005年9月5日発行)
出産に際して知っておきたいこと | 国立成育医療研究センター
分娩開始のサイン3:破水
胎児を包んでいた卵膜が破れて、羊水が外に流れ出てくることです。
「パンッ」という音を感じる場合もあれば、膣から羊水がちょろちょろと流れ出て初めて気づくケースもあります。
破水した場合は、清潔なナプキンをあて、すぐに分娩予定の医療機関へ連絡をしましょう。
ちなみに破水後の入浴やシャワーは厳禁です。
なかには尿漏れやおりものとの区別がつかない場合もあるため、判断できない場合も医療機関へ連絡しましょう。
自然分娩の流れ3ステップ

分娩のサインから胎児が産まれてくるまでの過程は、どのようになっているのでしょうか。
分娩の進み方は、「分娩第1期~分娩第3期」の3つに分けられます。
順番に見ていきましょう。
分娩第1期
陣痛の始まりから子宮口が全開大になるまでの期間を分娩第1期といいます。
陣痛が始まってから分娩第一期をぬけるまでの所要時間は初産で「約13時間」です。
さらに分娩第1期は4つの段階に分かれているため、順番に解説していきます。
出典:
出産に際して知っておきたいこと | 国立成育医療研究センター
潜伏期
子宮口が0~2.5cmになるまでの段階です。陣痛の間隔は10分以内(1時間に6回以上)ですが、まだ耐えられる程度の痛みで持続時間もまだ短いです。
加速期
子宮口が2.5~4cm開くまでの段階です。陣痛は5~6分間隔になり、強さもだんだん増していきます。
極期
子宮口が8 ~10cm開くまでの段階です。
お産の過程でも一番苦しい時期といえます。陣痛は約3分毎となり持続時間も長くなっていきます(※9)。
赤ちゃんの頭が、骨盤の中に深く入ってきますから、いきみたくなる間隔が出てくることが多いです。
減速期
子宮口が約9~ 10 cmになるまでの段階です。児頭がさらに骨盤内に下がってきます。
分娩第1期の過ごし方のポイント
この時期は陣痛をいかに乗り越えるかが大切です。
痛みでパニックにならないように、一番楽な姿勢を探して痛みを逃していきます。
また、ここで体力を使い切ってしまうと微弱陣痛になって分娩が長引いたり、出産時に力が入らなかったりという状況になってしまいます。
呼吸法やリラックス法を上手に活用して、リラックスして過ごすようにしましょう。
陣痛の合間に行う食事や水分補給も大切です。
分娩第1期で注意が必要な症状
下記のような症状がつづく場合は、注意が必要です。
・腹痛がつづく
・おなかが板のように固い
・胎児の胎動が感じられない
上記の症状とともに少量の出血がみられた場合は、出産よりも先に胎盤がはがれてしまう「常位胎盤早期剥離」の可能性があります。
胎児と母体の命にかかわる危険な状態であり、大至急の対応が必要です。
すぐにかかりつけの医療機関へ連絡しましょう。
ほかにもいつもと違う症状を感じたり、判断に迷ったりする場合は、遠慮せずにかかりつけの医療機関に相談するようにしてください。
分娩第2期
子宮口が全開大になってから胎児が出てくるまでの期間です。
胎児の頭が骨盤に入り、旋回しながらゆっくりと出てきます。
初産の場合、分娩2期の所要時間や陣痛の間隔などは以下のとおりです。
所要時間 :2~3時間
陣痛の間隔 :2分前後
陣痛の持続時間:60~90秒
陣痛は分娩1期よりもさらに強くなり、いきみたいという感覚が出てくるため、医師や助産婦の指示に従っていきみます。
徐々に陣痛のときに胎児の頭が見え隠れするようになるでしょう。
会陰部に大きなかたまりがはさまったように感じるようになり、痛みも最大に強くなります。
最後には陣痛と陣痛の合間のときでも、胎児の頭は引っ込まず見えたままの状態になります。
この状態になったら、手を胸の上に組んで短い呼吸をし、いきまず全身の力を抜きましょう。
赤ちゃんは頭を旋回させながら、顔を下に向けて生まれてきます。
体の中でいちばん大きい頭が産道をくぐり抜ければ、続いて肩、腕、胴体、脚と出てきます。
分娩第3期
胎児が産まれてから胎盤が出てくるまでの期間であり、所要時間は「15~30分」です。
赤ちゃんが産まれると子宮は収縮し、おへその部分まで下がってきます。
しばらくすると、後陣痛と呼ばれる子宮の収縮が起こり、胎盤がはがれて出てきます。
【しばらくは安静】分娩後の生活

初産で自然分娩の場合、産後の入院期間は5~6日です。
お母さんはこの期間に分娩後の体を休め、沐浴や授乳など赤ちゃんのお世話の指導を受けます。
退院後1~2週間はできる限り安静に過ごしましょう。
赤ちゃんの睡眠時間に合わせて寝起きし、しっかりと休息をとりましょう。十分な休息が産後うつの予防にもつながります。
産後1ヶ月検診で体に問題がなければ普段の生活に戻ることができます。
しかし、体の回復には6~8週間かかります。無理をせず、少しずつ体調を整えていきましょう。
まとめ
分娩にかかる時間には個人差があります。
分娩に異常があるかどうかは、所要時間だけでなく、胎児の大きさや姿勢、陣痛の強さなど色々な要因によって判断されるのです。
標準より早かったり遅かったりしても、それだけで不安になる必要はありません。
また、陣痛中はとても辛く感じると思いますが、痛みを感じているときは同時に赤ちゃんも頑張っていることを思い出してください。
お母さんとお父さんに会おうと必死に頑張っている赤ちゃんのことを思うと、自然と力も湧いてくるものです。
新しい命の誕生を迎えるその瞬間まで、リラックスしながらマタニティライフを楽しみましょう。
チャンスは出産時の一度きり。赤ちゃんの将来の安心に備えるさい帯血保管とは

もうすぐ出産。産まれてくる赤ちゃんのために、赤ちゃんがおなかにいる今しか準備できないことがあるのをご存知ですか?
それが「さい帯血保管」です。
さい帯血とは、赤ちゃんとお母さんを繋いでいるへその緒を流れている血液のことです。この血液には、「幹細胞」と呼ばれる貴重な細胞が多く含まれており、再生医療の分野で注目されています。このさい帯血は、長期にわたって保管することができ、現在は治療法が確立していない病気の治療に役立つ可能性を秘めています。
保管したさい帯血が、赤ちゃんやご家族の未来を変えるかもしれません。しかし採取できるのは、出産直後のわずか数分間に限られています。採血と聞くと痛みを伴うイメージがあるかと思いますが、さい帯血の採取は赤ちゃんにもお母さんにも痛みはなく安全に行うことができます。
民間さい帯血バンクなら、赤ちゃん・家族のために保管できる
さい帯血バンクには、「公的バンク」と「民間バンク」の2種類があり、公的バンクでは、さい帯血を第三者の白血病などの治療のために寄付することができます。
一方民間バンクでは、赤ちゃん自身やそのご家族の将来のために保管できます。現在治療法が確立されていない病気に備える保険として利用できるのが、この民間さい帯血バンクです。
ステムセル研究所は、国内シェア約99%を誇る国内最大の民間さい帯血バンクです。
ステムセル研究所が選ばれる理由

・1999年の設立以来20年以上の保管・運営実績あり
・民間バンクのパイオニアで累計保管者数は7万名以上
・全国各地の産科施設とのネットワークがある
・高水準の災害対策がされた国内最大級の細胞保管施設を保有
・厚生労働省(関東信越厚生局)より特定細胞加工物製造許可を取得
・2021年6月東京証券取引所に株式を上場
詳しい資料やご契約書類のお取り寄せは資料請求フォームをご利用ください。
さい帯血を保管した人の声
■出産の時だけのチャンスだから(愛知県 美祐ちゃん)
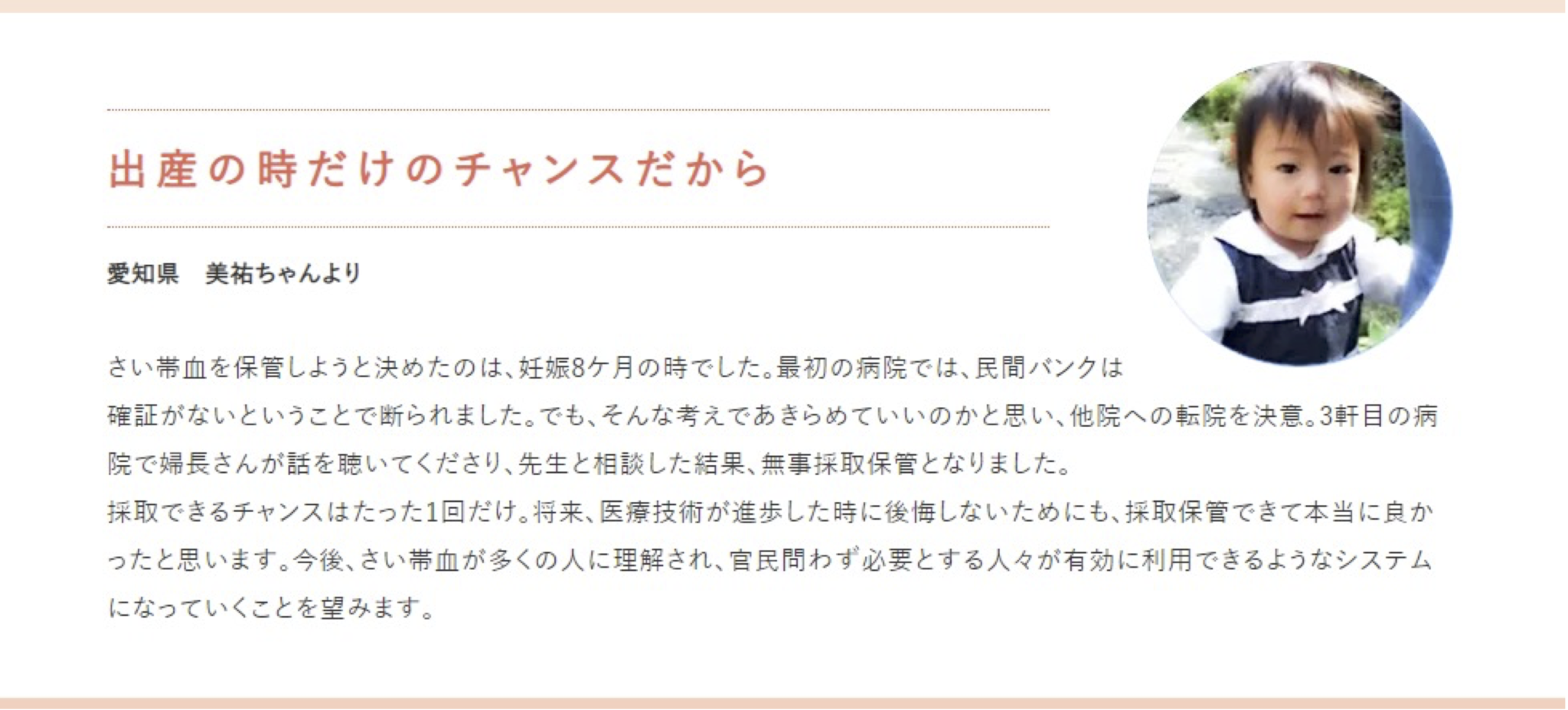
■さい帯血が本当の希望になりました(東京都 M・Y様)
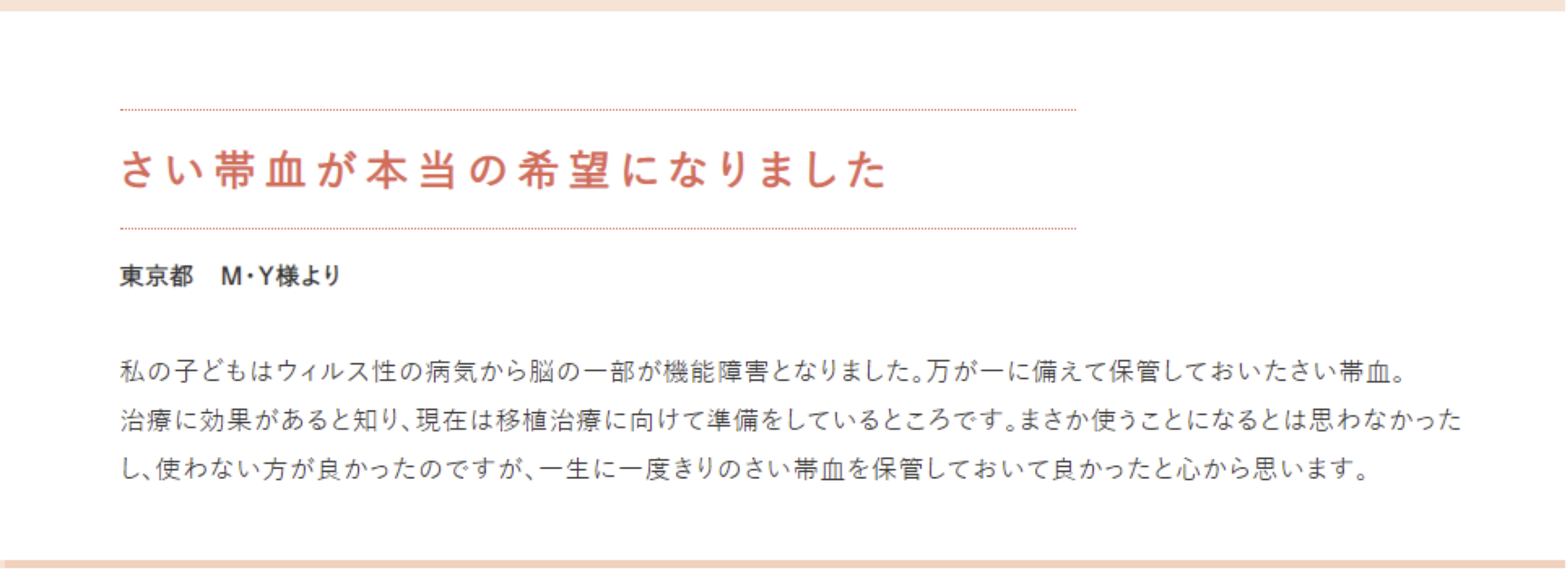
※ほかの保管者のから声はこちら
さい帯血保管は、赤ちゃんへの「愛」のプレゼント。
心も体も出産に向けた準備をしながら、赤ちゃんに会えるまでのもう少しの期間、ぜひ幸せな気持ちで過ごしてくださいね。
▼さい帯血保管について、もっと詳しく
この記事の監修者

坂田陽子
経歴
葛飾赤十字産院、愛育病院、聖母病院でNICU(新生児集中治療室)や産婦人科に勤務し、延べ3000人以上の母児のケアを行う。
その後、都内の産婦人科病院や広尾にある愛育クリニックインターナショナルユニットで師長を経験。クリニックから委託され、大使館をはじめ、たくさんのご自宅に伺い授乳相談・育児相談を行う。
日本赤十字武蔵野短期大学(現 日本赤十字看護大学)
母子保健研修センター助産師学校 卒業
資格
助産師/看護師/国際認定ラクテーションコンサルタント/ピーターウォーカー認定ベビーマッサージ講師/オーソモレキュラー(分子整合栄養学)栄養カウンセラー