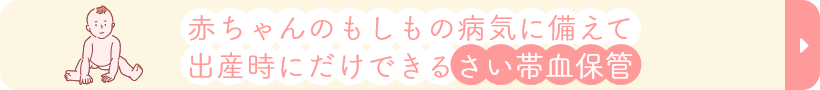「無痛分娩は、本当に無痛なのだろうか」
無痛分娩を決めた人や無痛分娩にしようか迷っている人が一番気になるポイントですよね。
結論からいうと、痛みを感じるかは個人によります。
麻酔のタイミングや効き目によっても、痛み具合は変わるのです。
この記事では、おもに以下の内容を解説していきます。
・無痛分娩で痛みを感じる理由
・無痛分娩をした人の体験談
この記事を読むと、無痛分娩で出産するかを検討できるようになりますよ。
無痛分娩の痛みは麻酔で緩和される

無痛分娩で使用される代表的な麻酔は「硬膜外麻酔」であり、
背骨の奥にある硬膜外腔にカテーテルを入れて麻酔を行う方法です。
カテーテルとは医療用の柔らかいチューブみたいなものをさします。
痛みの強さは最初にチクッとするだけで、予防接種くらいです。
しかし硬膜外腔はとてもデリケートな箇所であるため、ちょっとずれると大変なことに。
そのため、硬膜外麻酔は専門の麻酔科医がやることの多い麻酔なのです。
そのほかにも「点滴麻酔」がありますが、効き目が弱いため硬膜外麻酔がメインに使用されています。
無痛分娩で痛みを感じる理由とは?

無痛分娩では通常、計画分娩になることが多く、経過をみて予定した日にちに入院します。
自然なタイミングを待っていると、麻酔科医の不在などで無痛分娩の処置ができない可能性があるためです。
そして計画分娩では陣痛を誘発する「陣痛促進剤」を使うケースが多いです。
入院後、まずは陣痛促進剤を入れて、陣痛を起こします。
その後に麻酔を入れて、分娩台へと上がり出産、という流れです。
さて本題の「痛み」ですが、上記の説明で、お気づきになりましたか?
「陣痛を起こしてから麻酔」なのです。
陣痛=痛い、わけですから「痛みはある」ということになります。
痛みはどれくらい我慢すればいいの?無痛分娩で麻酔を入れるタイミング

大抵は子宮口3~5cm程度に開いた頃です(※1)。
病院や先生の方針や、分娩の進み具合にもよって異なります。
陣痛は一定の間隔で起こり、出産が近付くほど間隔が短くなっていきます。
一般的に初産婦さんは時間がかかり、長い方では陣痛から出産まで1日かかる人も(※2)。
麻酔のタイミングは、出産する病院で確認し、心の準備をしておくとよいですね。
出典
(※1)麻酔科医が担当する硬膜外無痛分娩|独立行政法人国立病院機構 京都医療センター
無痛分娩の痛みは分娩が進むと強くなることも

子宮口が全開となり、ついに赤ちゃんが産まれるときが、最も痛い場面です。
ここでは、麻酔がしっかり効いてくれないと困りますよね。
じつは、痛みの強さに合わせて麻酔の量は調節するものなのです。
しかし「いきむ」ためには、運動機能が麻痺するほどの麻酔はかけられません。
痛みはとるのに力が入るようにするなんて、なんて難しい麻酔なのでしょうか。
無痛分娩のニーズ増加に伴い、熱心に訓練された産科医の方が麻酔をされるケースが増えています。
しかし痛みの経過を見ながら麻酔の量をコントロールするには、専門家がいて、人員が整っていることも重要です。
病院を選ぶ際は、常駐の麻酔科医(できれば産科専門の麻酔科医)がいるところを選ぶと安心ですね。
【体験談】無痛分娩の痛み、実際のところどうだった?

実際に、筆者の知人で無痛分娩を体験した人たちから、痛みの感じ方について体験談を聞きました。
「私の場合、計画無痛分娩だったのですが、前日から弱い陣痛が始まっていました。そのため診察を終えて麻酔を打つころには、もうかなり陣痛がきつくなっていて。我慢できない生理痛のような痛みが、3~5分間隔くらいできていました。10分程して先生がきてくれて、麻酔を打ってもらうと、ほんの数分で痛みがすーっとなくなりました。子宮がキューっと収縮しているのはわかるのですが、痛みはまったくないという不思議な感覚。1人目のときは自然分娩で、この痛みのピークに1日以上耐えたことがしんどくてトラウマ級だったので、無痛分娩にして本当によかったです。(30代女性)」
「無痛分娩にしましたが、初めは効きが悪かったのか、あまり痛みがなくなりませんでした。手元の点滴で自分で麻酔量を調節できたので、麻酔を少し増やすと痛みがなくなりました。ただ今度はいきむ感覚がわからなくて、助産師さんの掛け声にあわせていきんだものの、出産した実感が湧かず。無痛分娩にしてよかったですが、私は出産の思い出としてはちょっと物足りないものになりました。(30代女性)」
いずれも個人の感想ですが、「痛みがなくなってよかった」という意見もある一方、「痛みがなかったことで物足りなかった」と感じる人もいるようです。
いずれも、麻酔が効き始めるまでは、多少の痛みを感じることがあるようですね。
まとめ
無痛分娩は硬膜外麻酔を使います。
特に自然分娩を経験した妊婦さんにとっては痛みが軽減されていることが比較できますが、初産の方にとってはその痛みの度合いを想像するのは簡単ではないでしょう。
処置には技術が必要ですが、一度カテーテルを通せば麻酔の量を調整することも可能です。
無痛分娩であっても初めから全く痛みが無いわけではありませんが、陣痛が自分にとって耐えられない痛みである時は、医師へ相談し麻酔を増やすなど痛みをコントロールすることができます。
特に痛みに弱いから出産に不安を感じているのであれば無痛分娩を選択することを検討してみると良いでしょう。
チャンスは出産時の一度きり。赤ちゃんの将来の安心に備えるさい帯血保管とは

うまれてくる赤ちゃんのために、おなかに赤ちゃんがいる今しか準備できないことがあるのをご存知ですか?
それが「さい帯血保管」です。さい帯血とは、赤ちゃんとお母さんを繋いでいるへその緒を流れている血液のことです。この血液には、「幹細胞」と呼ばれる貴重な細胞が多く含まれており、再生医療の分野で注目されています。
このさい帯血は、長期にわたって保管することができ、現在は治療法が確立していない病気の治療に役立つ可能性を秘めています。保管したさい帯血が、赤ちゃんやご家族の未来を変えるかもしれません。
しかし採取できるのは、出産直後のわずか数分間に限られています。採血と聞くと痛みを伴うイメージがあるかと思いますが、さい帯血の採取は赤ちゃんにもお母さんにも痛みはなく安全に行うことができます。
民間さい帯血バンクなら、赤ちゃん・家族のために保管できる
さい帯血バンクには、「公的バンク」と「民間バンク」の2種類があり、公的バンクでは、さい帯血を第三者の白血病などの治療のために寄付することができます。
一方民間バンクでは、赤ちゃん自身やそのご家族の将来のために保管できます。現在治療法が確立されていない病気に備える保険として利用できるのが、この民間さい帯血バンクです。
ステムセル研究所は、国内シェア約99%を誇る国内最大の民間さい帯血バンクです。
ステムセル研究所が選ばれる理由

- ・1999年の設立以来20年以上の保管・運営実績あり
- ・民間バンクのパイオニアで累計保管者数は7万名以上
- ・全国各地の産科施設とのネットワークがある
- ・高水準の災害対策がされた国内最大級の細胞保管施設を保有
- ・厚生労働省(関東信越厚生局)より特定細胞加工物製造許可を取得
- ・2021年6月東京証券取引所に株式を上場
詳しい資料やご契約書類のお取り寄せは資料請求フォームをご利用ください。
さい帯血を保管した人の声
■出産の時だけのチャンスだから(愛知県 美祐ちゃん)
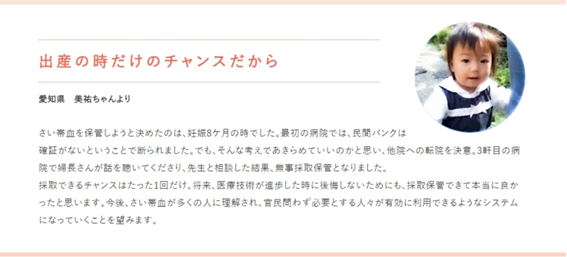
■さい帯血が本当の希望になりました(東京都 M・Y様)
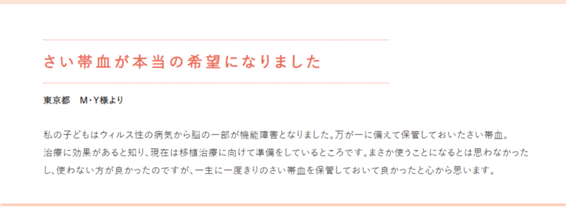
※ほかの保管者のから声はこちら
さい帯血保管は、赤ちゃんへの「愛」のプレゼント。
赤ちゃんに会えるまでのもう少しの期間、ぜひ少しでも快適に、幸せな気持ちで過ごしてくださいね。
▼さい帯血保管について、もっと詳しく
この記事の監修者

坂田陽子
経歴
葛飾赤十字産院、愛育病院、聖母病院でNICU(新生児集中治療室)や産婦人科に勤務し、延べ3000人以上の母児のケアを行う。
その後、都内の産婦人科病院や広尾にある愛育クリニックインターナショナルユニットで師長を経験。クリニックから委託され、大使館をはじめ、たくさんのご自宅に伺い授乳相談・育児相談を行う。
日本赤十字武蔵野短期大学(現 日本赤十字看護大学)
母子保健研修センター助産師学校 卒業
資格
助産師/看護師/国際認定ラクテーションコンサルタント/ピーターウォーカー認定ベビーマッサージ講師/オーソモレキュラー(分子整合栄養学)栄養カウンセラー