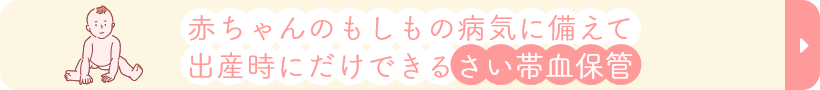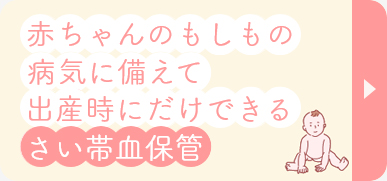初めての帝王切による出産をひかえているが、体調が回復するまでどれくらいかかるのだろうと考えていませんか。
体調の回復までには「約8日」かかるといわれていますが、個人差があり、長引いてしまうことも。
しかし、回復を早めるためにできることはあります。
この記事では、おもに以下の内容を解説していきます。
・帝王切開後の回復までにかかる時間
・回復を早める方法
・帝王切開後の生活で注意すべき行動
この記事を読むと、帝王切開後の生活における不安や心配がやわらぎますよ。
帝王切開後の体調回復(退院)まで【約8日】

帝王切開はおなかを切る手術なので、麻酔が切れた後は傷口に痛みが出て、回復までに「6~10日」必要です。
産後の体調によっては術後10日以上入院することもあり、回復には個人差があります。
術後2~3日は傷口の痛みも強いため、無理せず安静に過ごしましょう。
帝王切開後の傷跡が治るまで【3ヵ月~1年】

傷口は術後3日くらいで閉じてきます。
体質等により個人差はありますが、肌の色に近い傷痕になるまで3カ月から1年はかかるでしょう。
抜糸や抜鈎が終わったらケアを始めるタイミングです。
ポイントは伸展刺激の抑制(皮膚を伸ばさないようにすること)。
専用テープでケアすると、皮膚が赤く盛り上がる「肥厚性瘢痕」や「ケロイド」を防げます。
帝王切開の産後の傷跡ケア
帝王切開の産後に大切なこととして、傷跡のケアがあります。帝王切開の傷跡は残りやすいと言われています。傷口は術後3日くらいで閉じてきます。体質等により個人差はありますが、肌の色に近い傷痕になるまで3カ月から1年はかかるといわれています。
抜糸や抜鈎が終わったらケアを始めていきましょう。ポイントは伸展刺激の抑制(皮膚を伸ばさないようにすること)です。専用テープでケアすることで皮膚が赤く盛り上がる肥厚性瘢痕やケロイドを防ぐことができます。
帝王切開後の回復を早める方法【5選】

方法1:十分な睡眠をとる
帝王切開での出産も自然分娩と同様に出産したことによる体への負担は大きいです。
それに加え傷口の回復を待ちながら赤ちゃんのお世話も始まります。
そうなると体を休める時間はとても貴重です。出産直後は興奮状態で元気そうに思えますが、時間の許す限り睡眠をとって体を回復させることを優先させましょう。
方法2:栄養がある食事をとる
帝王切開後は3~5日で普通食となります。
退院後も栄養のある食事を心がけましょう。
産後の体が回復するまでには6週間以上かかります。なおかつ術後の傷跡があるため傷の回復のためにも栄養をつけましょう。
「鉄分」
貧血の防止に鉄分は欠かせません。妊娠中からの貧血や出産時の出血、授乳などで鉄分が失われる機会がとても多いです。意識して摂るようにしましょう。
「葉酸」
妊娠前にも摂ると良いとさえていた葉酸は産後にも必要な栄養です。これは赤血球を作るために必要な栄養素なので貧血の防止になります。
方法3:毎日歩く
傷口の痛みの程度によりますが、手術翌日から歩行可能です。悪露やガスを早く体外へ出したり、血栓ができることを防いだり、癒着を防いだりするためにはなるべく術後早いうちから体を動かすことが必要です。
術後すぐはトイレに行くまでの短い距離から始めて、少しずつで良いので歩けるように努力しましょう。
方法4:傷口を清潔に保つ
手術直後は傷の上に専用のテープを貼ります。
傷自体は3日ほどでふさがりますが、その後赤くなる炎症期を経て目立たなくなるまでには1年ほどかかります。
傷跡の固定や保護のためにテープを貼っておき、数日に一回交換すると傷がきれいに治っていきます。
その際傷は清潔にシャワーで流しましょう。
傷を治すための血球の働きも妨げるしまうので、最近では傷の消毒は行わず水で洗い流し清潔に保つことが基本となっています。
方法5:締め付けがない服を着る
傷に貼るテープにも効果がありますが、傷跡がこすれると摩擦によって傷の治りが遅くなったり痒みが出たりします。
術後しばらくは、マタニティ用の下着やズボンなど締め付けのないゆったりとした服を着ることをお勧めします。
帝王切開後の回復が遅くなる!?生活で注意すべき行動

帝王切開後の生活では、身体に負担をかけずに生活することが大切です。
産後約1ヵ月は、しゃがんだり、重いものを持ったりなど、おなかに力を入れる行動をとると傷口が痛む可能性があります。
家事代行やネットスーパー、宅食サービスなど利用しながら、身体に負担のかからない生活を送るのがベストです。
「産後3週間」を過ぎる頃からは、痛みなどが落ち着いていれば、少しずつ軽い家事などは始めてもよいでしょう。
ただし育児を優先し、そのほかの家事は少し手を抜くか、家族に協力してもらい負担を減らしましょう。
「車の運転」も身体に負荷がかかるので注意が必要です。
また性行為についても、帝王切開の場合は術後「2カ月以上」控えるよう医師から指示されるケースもあります。
術後の身体に負担がかからないよう気をつけましょう。
帝王切開後の回復期間の過ごし方FAQ

帝王切開後の回復期間の過ごし方について、よくある質問と回答をご紹介します。
Q:帝王切開後に痛み止め薬を飲用しながら授乳しても大丈夫?
A:術後、痛み止めの薬を飲んでいる場合、授乳を迷う方もいるかもしれませんが、産院で処方される薬は適切に飲めば赤ちゃんへの影響はほとんどありません。
市販薬などを飲む場合は医師に相談してください。
Q:帝王切開後に産褥ショーツは必要?
A:出産直後はベッドに寝た状態でナプキンの交換や医師の診察があるため、脱がずに過ごすことができる産褥ショーツはあると便利です。いろいろなタイプがありますが、特に帝王切開後の場合は全開タイプがおすすめ。
また産褥ショーツは股上部分が深いもの、柔らかいガーゼ素材になっているものなど、傷跡への負担が少ないデザインになっています。
入院期間分は用意しておくと安心でしょう。
帝王切開後の回復を早めるために活用したいサポート

「産前・産後サポート事業」や「産後ケア事業」をご存じですか。
妊産婦や乳幼児が安心して健康な生活ができるよう、国のガイドラインに沿って各市町村が支援のためのサービスを行っています。
地域の保健師、助産師、看護師、保育士、管理栄養士、心理士などの専門的な知識を持った人のほかに、子育て経験者や地域の人が連携して利用者目線に立った一貫性、整合性のある支援を実現することを目指したサービスです。
産後ケア事業ではあなたの
・身体的な回復のための支援
・授乳の指導及び乳房のケア
・不安や悩みを傾聴する
などの心理的支援、新生児及び乳児の状況に応じた具体的な育児指導、家族等の身近な支援者との関係調整、地域で育児をしていくうえで必要な社会的資源の紹介など具体的な支援を行っています。
各事業によってサービスの種類もさまざまです。
産前・産後サポート事業では、下記2つのタイプがあります。
・アウトリーチ型(利用者宅への訪問、電話、メールによる個別の相談など)
・集団型(支援センターなどに集まって集団で相談や交流を行う)
また産後ケア事業には、
・ショートステイ型(病院や病床施設のある診療所などに宿泊しながらケアを受ける)
・デイサービス型(病院や診療所、助産所、保健センターなどで個別または集団でケアを受ける)
・アウトリーチ型(自宅でケアを受けるタイプ)
の3種類があります。
自分に合ったサービスを探し、うまく活用してみましょう。
帝王切開後の妊娠については医師と相談する

帝王切開後の妊娠は、一般的には6ヵ月空ければ問題ないとされています。
しかし妊娠、出産するには、体の回復が万全で周囲の十分なフォローや協力があり、心身共に余裕をもって生活できる状態であることが大切です。
また帝王切開で出産した経験がある場合、子宮破裂を起こすリスクがあります。
手術で赤ちゃんを取り出すために切開して縫い合わせた子宮の傷が次回の妊娠で裂ける可能性があるからです。
また子宮の傷は治っていたとしても切開した箇所は周りの子宮壁に比べて薄く脆弱になっているため、子宮破裂が起こる可能性があります。
子宮破裂で最も多くみられるのが、帝王切開による出産を経験した方が次の出産で経腟分娩を行ったケースです。
次回の妊娠で経腟分娩を検討している方は、よく医師と相談するようにしましょう。
まとめ
帝王切開はおなかを切開する手術であるため、身体の負担は普通分娩より大きい状態にあります。
産後は育児や家事を完璧に行おうとせずに、赤ちゃんと自分の身体のことを優先的に考えるようにしましょう。
家族に協力してもらえると良いのですが、難しい場合には各市町村が行っている産前・産後サポート事業や産後ケア事業のサービスを活用し、一人で抱え込まないようにしましょう。
チャンスは出産時の一度きり。赤ちゃんの将来の安心に備えるさい帯血保管とは

うまれてくる赤ちゃんのために、おなかに赤ちゃんがいる今しか準備できないことがあるのをご存知ですか?
それが「さい帯血保管」です。
さい帯血とは、赤ちゃんとお母さんを繋いでいるへその緒を流れている血液のことです。この血液には、「幹細胞」と呼ばれる貴重な細胞が多く含まれており、再生医療の分野で注目されています。
このさい帯血は、長期にわたって保管することができ、現在は治療法が確立していない病気の治療に役立つ可能性を秘めています。保管したさい帯血が、赤ちゃんやご家族の未来を変えるかもしれません。
しかし採取できるのは、出産直後のわずか数分間に限られています。採血と聞くと痛みを伴うイメージがあるかと思いますが、さい帯血の採取は赤ちゃんにもお母さんにも痛みはなく安全に行うことができます。
民間さい帯血バンクなら、赤ちゃん・家族のために保管できる
さい帯血バンクには、「公的バンク」と「民間バンク」の2種類があり、公的バンクでは、さい帯血を第三者の白血病などの治療のために寄付することができます。
一方民間バンクでは、赤ちゃん自身やそのご家族の将来のために保管できます。現在治療法が確立されていない病気に備える保険として利用できるのが、この民間さい帯血バンクです。
ステムセル研究所は、国内シェア約99%を誇る国内最大の民間さい帯血バンクです。
ステムセル研究所が選ばれる理由

・1999年の設立以来20年以上の保管・運営実績あり
・民間バンクのパイオニアで累計保管者数は7万名以上
・全国各地の産科施設とのネットワークがある
・高水準の災害対策がされた国内最大級の細胞保管施設を保有
・厚生労働省(関東信越厚生局)より特定細胞加工物製造許可を取得
・2021年6月東京証券取引所に株式を上場
詳しい資料やご契約書類のお取り寄せは資料請求フォームをご利用ください。
さい帯血を保管した人の声
■出産の時だけのチャンスだから(愛知県 美祐ちゃん)
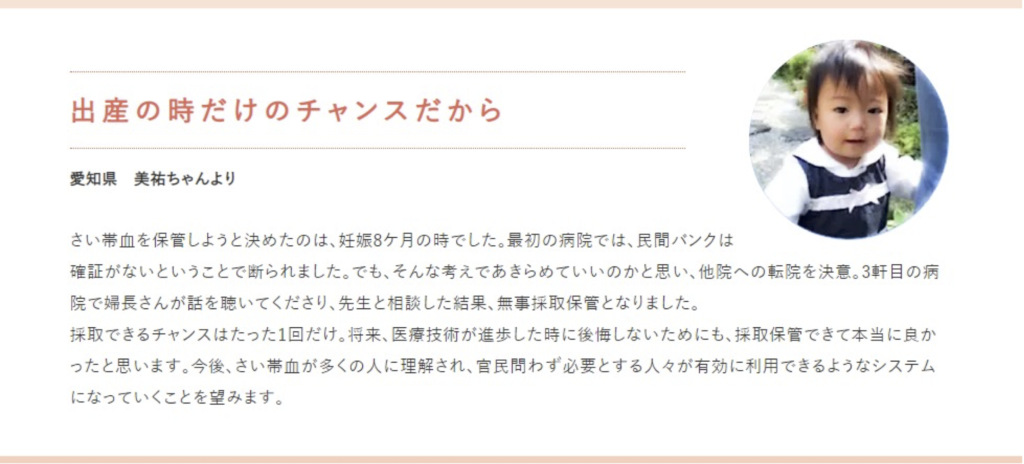
■さい帯血が本当の希望になりました(東京都 M・Y様)
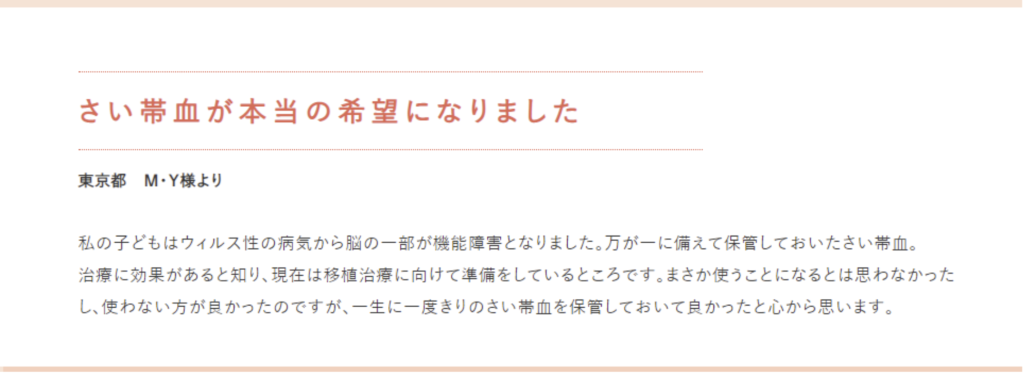
※ほかの保管者のから声はこちら
さい帯血保管は、赤ちゃんへの「愛」のプレゼント。
赤ちゃんに会えるまでのもう少しの期間、ぜひ少しでも快適に、幸せな気持ちで過ごしてくださいね。
▼さい帯血保管について、もっと詳しく
この記事の監修者

坂田陽子
経歴
葛飾赤十字産院、愛育病院、聖母病院でNICU(新生児集中治療室)や産婦人科に勤務し、延べ3000人以上の母児のケアを行う。
その後、都内の産婦人科病院や広尾にある愛育クリニックインターナショナルユニットで師長を経験。クリニックから委託され、大使館をはじめ、たくさんのご自宅に伺い授乳相談・育児相談を行う。
日本赤十字武蔵野短期大学(現 日本赤十字看護大学)
母子保健研修センター助産師学校 卒業
資格
助産師/看護師/国際認定ラクテーションコンサルタント/ピーターウォーカー認定ベビーマッサージ講師/オーソモレキュラー(分子整合栄養学)栄養カウンセラー