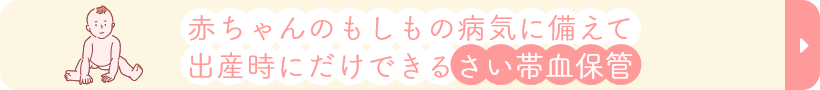妊娠後期に入り出産をひかえているが、出産準備では最低限なにが必要なのだろうかと悩んでいませんか。出産準備では、かならず用意しておきたいものが6点あります。また赤ちゃんが生まれる季節によって、追加で準備しておきたいものもあるのです。
この記事では、おもに以下の内容を解説していきます。
■最低限必要な出産準備リスト
■【季節別】出産準備リスト
■出産準備の体験談
この記事を読むと、安心して出産を迎えられるようになりますよ。
【絶対確認】最低限必要な出産準備リスト

かならず用意しておきたいものとしては、おむつ、おしりふき、お風呂グッズ、爪切り、消毒液、体温計の6つになります。
□おむつ
□おしりふき
□お風呂グッズ(ベビーソープ、ベビーバス、ガーゼ、綿棒)
□爪切り
□消毒液
□体温計
|
準備品 |
備考 |
|
おむつ |
1~2パック準備しましょう。 サイズやお肌に合うかなどの相性がある為、様子をみて買い足すと良いかと思います。 |
|
おしりふき |
2~4個準備しましょう。 お肌に合うか等、様子をみながら買い足しましょう。
|
|
バスグッズ |
ベビーバスを1カ月検診までは、衛生面の為に使用します。 ベビーソープは、赤ちゃん用の低刺激なものを選びましょう。 ガーゼは、大きめのものを、赤ちゃんにかけて使用し、小さめのものを体を洗う際に使用します。 綿棒はお臍のケアなどに使用します。 |
|
爪切り |
ベビー用の先が丸くなったものが良いでしょう |
|
消毒液 |
赤ちゃんのお臍のケアの時などに使用します。 |
|
体温計 |
非接触型の体温計など、短時間で測れるものがおすすめです。 |
最低限必要なものを揃えるための費用【約30万円】
必要最低限の物を準備し、またベビーウエアや抱っこ紐なども準備すると、個人差はありますが、年間で考えると30万円ほどになる計算になると言われています。最初から、全て揃えよとすると手間も費用も膨らんでしまいますので、赤ちゃんの成長や、発達、ママとパパのライフスタイルに合わせて少しずつ揃えると無駄が少なくなり、費用を抑えることにつながります。
参考出産準備にかかる費用の平均はいくら?節約のポイントなども紹介 | ステムセル研究所 (stemcell.co.jp)
赤ちゃん用品の準備費用 年間 (※1)
|
ベビー用品 |
相場金額 |
|
ベビーウエア(肌着、外出着など) |
3万円程度 |
|
抱っこひもなどのお出かけ用品 |
3~5万円程度 |
|
オムツ、おしりふきなど |
6~13万円程度 |
|
ミルク、哺乳瓶など |
6万円程度 |
|
ベビーバスなどのお風呂グッズ |
1万円程度 |
※1)赤ちゃんの準備費用で実際にかかった金額と内訳まとめ | 保険の教科書 (hoken-kyokasho.com)
必要に応じて揃える出産準備リスト
「必要に応じて」準備するアイテムに関しては、本当に自分にとって必要かどうか、判断するのが難しいですよね。下記のリストに、必要に応じて準備するアイテムをご紹介しますが、ポイントとしては、赤ちゃんのご成長やご発達、個性、またご家族様の好みや、ライフスタイルに合わせて取捨選択できると良いかと思います。
□鼻水吸引器などの衛生品
□哺乳瓶、粉ミルク、消毒セット
□ベビーベッド、ベビー布団
□車のチャイルドシート
□ベビーカー
|
鼻水吸引器などの衛生品
|
赤ちゃんとの相性によっては使わない場合もあります。 |
|
哺乳瓶、粉ミルク、消毒セット
|
個人差が多いですが、完全母乳の場合でも急に粉ミルクが必要になる場合もあります。念のため最低限の哺乳瓶、粉ミルクを準備するのが良いです。 |
|
ベビーベッド、ベビー布団
|
ベビーベッドは、お世話の時に、楽におむつ替えなども行えます。赤ちゃんは、最初はほとんど寝て過ごしますので、ベビー布団は、安心して眠るための用品としてお揃えになるのが良いかと思います。 |
|
車のチャイルドシート
|
退院後に、自動車で自宅で戻られる場合は、必須になります。実際にお店で、重さや形状などを確かめて購入すると安心ですので、早めの準備がおすすめです。 |
|
ベビーカー
|
A型タイプは1カ月から使用できますので、生活スタイルに合わせて使い勝手の良いものを選ぶと良いかと思います。 |
|
抱っこ紐
|
様子をみて、ママも赤ちゃんも使いやすいものを選ぶのが一番かと思います。 |
【経験談】先輩ママからのアドバイス
沐浴のあと赤ちゃんを安全に寝かすスペースを予め考えておけばよかったと思っています。産院であれば、沐浴が終わるとすぐ隣にベビーベッドがあるため不備はありませんでした。
しかし自宅に帰ってからは、少し離れたリビングに行く前に身体拭きやおむつをする場所がない、と困りました(結局、お風呂場から出たすぐに、ベビークーファンを準備しました)。赤ちゃんとの実際の生活が始まるまでは、気付かないような事があり、出産後に赤ちゃんから教えてもらうことが多々ありました。

【季節別】出産準備リスト

出産に備えて用意するものの中でも、衣類については、暑さや寒さを考慮して季節別に考えたいと思います。春夏秋冬4シーン別に、準備したい衣類を紹介します。
【春生まれ】出産準備リスト
□短肌着
□長肌着
□コンビ肌着
□ツーウェイオール
肌寒い日や、あたたかい日が交互に訪れる春ですので、短肌着に重ねる長肌着も準備して保温できるようにしましょう。
夜間少し肌寒いときは肌着を2枚にしたり、スリーパーを着せたりして対応しましょう。
新生児期はおくるみも体温調節に便利です。
【夏生まれ】出産準備リスト
□短肌着
□ノースリーブ肌着
□長肌着
□コンビ肌着
夏生まれの場合は、日中は下着1枚で過ごすことが多くなります。
汗をかきやすい時期なので、下着を多めに用意しておくと安心です。
【秋生まれ】出産準備リスト
□短肌着
□長肌着
□コンビ肌着
□ロンパースまたはツーウェイオール
□ベスト
春生まれと同様、日中は短肌着+長肌着または肌着+コンビ肌着+ツーウェイオールかロンパースといった服装がおすすめです。
暑そうなときには1枚減らし、寒そうなときは肌着を1枚プラスして調整しましょう。ベストもあると脱着しやすく便利です。
【冬生まれ】出産準備リスト
□長肌着
□コンビ肌着
□ロンパースまたはツーウェイオール
冬生まれの場合でも、基本的には暖房器具で室温を調整し、赤ちゃんにはあまり厚着させないことが多いです。
赤ちゃんは体温調整機能が未熟で、汗っかきなため厚着はおすすめではありません。また厚手の素材は、赤ちゃんの動きを妨げてしまうこともあるため、厚着させないのが良いです。
長肌着+ロンパースといった服装で十分です。
寝るときにはスリーパーや寝具、おくるみを使用して調整してあげましょう。
【体験談】ママのための出産準備

赤ちゃんだけではなく、ママにも出産準備が必要です。
私の体験をもとに、ママにおすすめの出産準備をご紹介します。
美容院など自分のケア
私の場合、出産から約1カ月は、自分の体力回復と赤ちゃんのお世話に追われて、ゆっくり外出したり、自分の時間を持ったりできなくなりました(もちろん忙しいとは聞いていましたが、これほどか、と思いました)。
そのため自分の時間を持つことを、出産準備リストの中に入れるのがおすすめです。
じつは、長男を出産したのは夏で、髪を切りに行きたかったのですが、3カ月ほど美容院に行けませんでした。
そのため2人目のときは、出産の準備の一つとして、美容院に行くと決めていました。出産の準備というと、いろいろな買い物や環境を整えることに頭が働いてしまいます。しかし出産後しばらくは、赤ちゃんとの新しい生活がはじまり、なかなか自分の時間がとれないかもしれません。
是非ともママの出産の準備の一つとして、私のように美容院に行くなど、自分の時間を作ってみましょう。
産後の手続き準備
産後に慌てないために、事務的な手続きなどを予め確認するよい時期だと思います。
たとえば出生届けの手続きについて、いつまでに、どこへ出しに行くかをチェックしておきましょう。
また、なるべく事務的なことは、ママだけが負担するのではなく、パートナーと分担するか、お任せすることをおすすめします。
産後は赤ちゃんのお世話とママの回復が第一であるためです。
そのほかにも、
- ・赤ちゃんの健康保険の加入の手続き
- ・出産育児一時金
- ・出産手当
などの手続きも、どのように申請するかを予め確認すると安心です。

出産の準備はいつから始めるべき?

9カ月以降は動きにくくなり、出産が予定日よりも早まる可能性もあります。
予定日間近のお買い物は何が起こるかわかりません。
予定日1カ月前には、ある程度揃えておくのが理想的です。
妊娠後期に入ると、お腹もますます大きくなり、大きな荷物を持つことや、長時間お出かけするのが難しくなってきます。なるべく、ご家族さまと一緒にお買い物されたり、ネット通販などを利用して、予定日1カ月前には、ある程度揃えておくのが理想的です。出産が予定日よりも早くなる可能性もありますし、予定日間際ですと何が起こるかわからない為、早めの準備がおすすめです。
まとめ
出産のご準備について、イメージ膨らみましたでしょうか。最低限に必要なものをご準備された後は、ご自分の生活スタイルに合わせて優先順位が高いものから選ばれると良いかと思います。赤ちゃんのお洋服やグッズは、かわいいものばかりですよ!赤ちゃんの為のお品を選ぶ作業を楽しんで頂けたら、何よりと思います。お体を大切になさって、良いご出産をお迎えください。
チャンスは出産時の一度きり。赤ちゃんの将来の安心に備えるさい帯血保管とは

うまれてくる赤ちゃんのために、おなかに赤ちゃんがいる今しか準備できないことがあるのをご存知ですか?
それが「さい帯血保管」です。
さい帯血とは、赤ちゃんとお母さんを繋いでいるへその緒を流れている血液のことです。この血液には、「幹細胞」と呼ばれる貴重な細胞が多く含まれており、再生医療の分野で注目されています。
このさい帯血は、長期にわたって保管することができ、現在は治療法が確立していない病気の治療に役立つ可能性を秘めています。保管したさい帯血が、赤ちゃんやご家族の未来を変えるかもしれません。
しかし採取できるのは、出産直後のわずか数分間に限られています。採血と聞くと痛みを伴うイメージがあるかと思いますが、さい帯血の採取は赤ちゃんにもお母さんにも痛みはなく安全に行うことができます。
民間さい帯血バンクなら、赤ちゃん・家族のために保管できる
さい帯血バンクには、「公的バンク」と「民間バンク」の2種類があり、公的バンクでは、さい帯血を第三者の白血病などの治療のために寄付することができます。
一方民間バンクでは、赤ちゃん自身やそのご家族の将来のために保管できます。現在治療法が確立されていない病気に備える保険として利用できるのが、この民間さい帯血バンクです。
ステムセル研究所は、国内シェア約99%を誇る国内最大の民間さい帯血バンクです。
ステムセル研究所が選ばれる理由

・1999年の設立以来20年以上の保管・運営実績あり
・民間バンクのパイオニアで累計保管者数は7万名以上
・全国各地の産科施設とのネットワークがある
・高水準の災害対策がされた国内最大級の細胞保管施設を保有
・厚生労働省(関東信越厚生局)より特定細胞加工物製造許可を取得
・2021年6月東京証券取引所に株式を上場
詳しい資料やご契約書類のお取り寄せは資料請求フォームをご利用ください。
さい帯血を保管した人の声
■出産の時だけのチャンスだから(愛知県 美祐ちゃん)
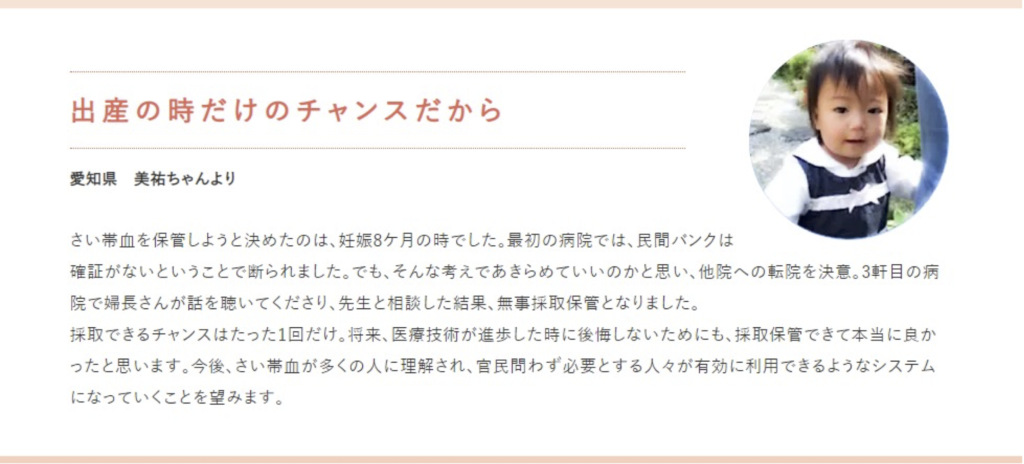
■さい帯血が本当の希望になりました(東京都 M・Y様)
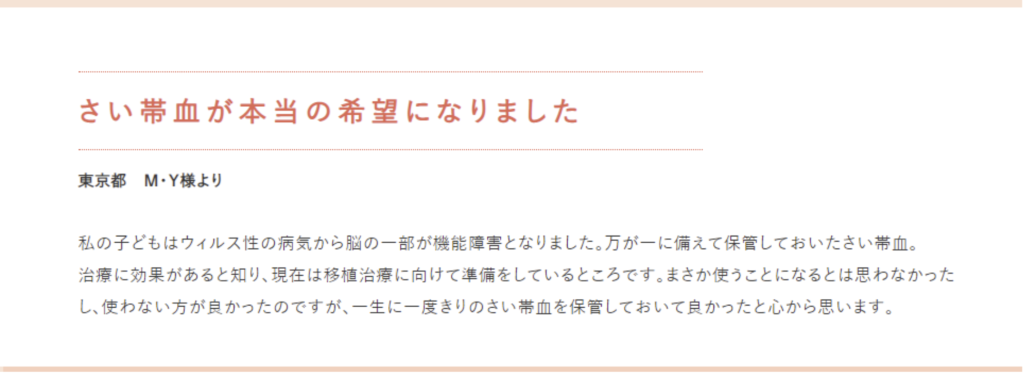
※ほかの保管者のから声はこちら
さい帯血保管は、赤ちゃんへの「愛」のプレゼント。
赤ちゃんに会えるまでのもう少しの期間、ぜひ少しでも快適に、幸せな気持ちで過ごしてくださいね。
この記事の監修者

坂田陽子
経歴
葛飾赤十字産院、愛育病院、聖母病院でNICU(新生児集中治療室)や産婦人科に勤務し、延べ3000人以上の母児のケアを行う。
その後、都内の産婦人科病院や広尾にある愛育クリニックインターナショナルユニットで師長を経験。クリニックから委託され、大使館をはじめ、たくさんのご自宅に伺い授乳相談・育児相談を行う。
日本赤十字武蔵野短期大学(現 日本赤十字看護大学)
母子保健研修センター助産師学校 卒業
資格
助産師/看護師/国際認定ラクテーションコンサルタント/ピーターウォーカー認定ベビーマッサージ講師/オーソモレキュラー(分子整合栄養学)栄養カウンセラー